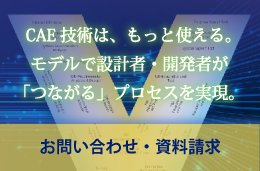受講者の声
トレーニング講座
Simcenter Flotherm XT入門(2日間)
講師からのメッセージ
本コースでは、Simcenter Flotherm XTを使った熱流体解析を実習を通して習得していただきます。実習には電子機器の様々な熱流体解析案件を想定したものを用意しました。この2日間が実務応用の基礎となるよう、ノウハウも織り交ぜながらわかりやすくご説明します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
Simcenter Flotherm XT入門(2日間) (オンライン版)
講師からのメッセージ
本コースでは、Simcenter Flotherm XTを使った熱流体解析を実習を通して習得していただきます。実習には電子機器の様々な熱流体解析案件を想定したものを用意しました。この2日間が実務応用の基礎となるよう、ノウハウも織り交ぜながらわかりやすくご説明します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
Simcenter Flotherm応用 収束性改善編(半日間)
講師からのメッセージ
本コースは、収束性改善に特化した内容になっています。基本的な考え方を習得し、大規模で複雑なモデルに対しても、収束性が良く解析時間が短いという、Simcenter Flothermの優位性を実感していただければ幸いです。
Simcenter Flotherm応用 収束性改善編(半日間)(オンライン)
講師からのメッセージ
本コースは、収束性改善に特化した内容になっています。基本的な考え方を習得し、大規模で複雑なモデルに対しても、収束性が良く解析時間が短いという、Simcenter Flothermの優位性を実感していただければ幸いです。
エレクトロニクスの熱設計概論 実践編(オンライン版)
講師からのメッセージ
熱設計スキルを向上させるためには、伝熱の基礎知識や熱設計の定石を知ることが不可欠です。本セミナーでは好評の熱設計クイズや演習問題を増やし、受講生参加型のセミナーとしています。”熱”は初めてという方、改めて基礎から学びたいという方、大歓迎です。
Thermocalc入門(オンライン版)
講師からのメッセージ
本コースでは、Thermocalcの内容と操作方法をご紹介します。また仮想製品の熱設計事例として、自然空冷機器、強制空冷機器の2ケースをご用意しました。熱設計プロセス上流でのThermocalcの使いどころ、熱設計の進め方などを分かりやすくご説明します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
熱設計CAE活用レベル比較・分析ワークショップ(1日間)
講師からのメッセージ
熱設計やCAEの活用方法は各企業の製品特性、組織体制、リソース、スキル、マネジメント方針などによって異なり、正解があるわけではありません。重要なことは他社事例などの情報(表面的な情報だけでなく実体情報)を集め、自社にあったプラニングを行うことです。
・他社の動向を知り、定量的に自社のポジショニングを行う
・他社の熱設計担当者、CAE推進者と知り合える情報交換の場を提供する
これらの情報を得て、今後のヒントとしていただくことが本ワークショップの目的です。皆様のご参加を心より待ちしております。
電子機器の温度測定とCAEのモデル化 導入編(オンライン版)
講師からのメッセージ
設計現場では熱流体シミュレーションと実測の乖離が問題になります。その場合、解析モデルが疑われがちですが、温度測定誤差や接触熱抵抗、放射率などの入力データの不正確さが原因であることも少なくありません。本コースではバーチャル実験(ビデオによる実験動画)を行いながら温度や熱特性の測定誤差、その対策などについて解説します。
電子機器の温度測定とCAEのモデル化 温度測定編(1日間)
講師からのメッセージ
実測とシミュレーションの結果が合わない場合、シミュレーションのモデルだけでなく、温度測定の条件も見直していますか? 本コースでは両者の誤差を抑える手法を学んでいただくことで、解析精度の向上にお役立ていただける内容になっています。 また、グループに分けて温度測定の実習をおこないますので、他社の熱設計エンジニアの方との情報交換の場としても、 有意義にご活用していただければと考えています。どうぞお気軽にご参加ください。
受講者の声
- 個人的に気になっている点について知ることができました。講義中に実施した実験と解析結果を比較することで問題を分かりやすく確認できて良かったです。(自動車)
- 実測の方法でこれほど誤差が出るとは思わなかった。普段なかなか実験できないので、良いセミナーだと思いました。(電気機器)
電子機器の温度測定とCAEのモデル化 接触熱抵抗編(1日間)
講師からのメッセージ
同コース「基礎編」には多くの方にご参加頂き、大変ご好評いただいています。解析精度を向上させるには、実験と解析を並行して行いながらその誤差をひとつずつ詰めていくことが大切です。「基礎編」では、温度測定もその方法によっ て大きな誤差を含むことがわかりました。部品と基板のモデルではポイントを押さえないと、簡単に数10℃程度の誤差が出ることもわかりました。今回の「自然空冷編」では、いよいよ機器筐体に実装したモデルを対象にします。スマホやECU、LED照明、薄型テレビのようなファンレス機器では、接触熱伝導を使った放熱が盛んにおこなわれるようになりましたが、解析でも「接触熱抵抗」を押さえない限り、正確な予測はできません。
理論的に把握しにくい、接触熱抵抗をテーマに実験と解析を行います。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
受講者の声
- 基本的な事柄からノウハウまで教授いただけて大変ありがたかった。(産業機械)
- 基礎実験を通して、熱設計への考え方が深まった。(設備機器・部品)
- 放熱シートの評価方法について知ることができた。また、解析設定について困っていたのであわせて知ることができた。(総合電機)
- 普段の業務ではCAE解析が主であるため、実験による比較検証ができて大変勉強になった。(総合電機)
- TIMの接触状態であんなにも温度差が生まれるとは思っていなかったため、大変良い経験ができた。(輸送機器)